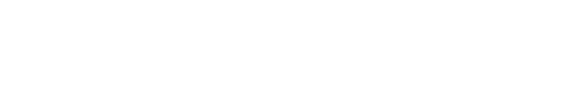これまでの第1回・第2回では、粘土や割り箸で模型を作ったり 、コンベックスで空間を測ったり、スケッチの技法を学んだりと、建築の基本的な技術を学んできました。
今回のテーマは、まさにその実践編!自然をありのままに見て感じ、自然の中で豊かなイメージを膨らませ、周りの人に伝えることを狙いとし、実際の場所でデザインを考えることに挑戦しました!
今回の授業内容
第3回 10月25日(土)
【計画】彩都の山でデザインを考えよう
施主の「想い」を聞いて、デザインを考えよう
今回の舞台は彩都の山にある「集いの広場」と呼ばれる場所。ここで、実際に山で活動する施主から、この広場に対する「想い」や「こうなったらいいな」という願いを聞きました。
施主の想いを受け取った子どもたちは、チームに分かれてさっそく活動スタート!
「どんなものがあったら、みんなが喜ぶかな?」 「この場所の特徴を活かすにはどうしたらいいだろう?」
第2回で学んだ「測量」を思い出しながらコンベックスで広場の大きさを測ってみたり 、第1回で学んだスケッチの技術を使ってその場の風景やアイデアを描いてみました。
机の上で学んだことを、実際の自然というフィールドで試行錯誤しながら「実践」する。 子どもたちは、まさに建築家が仕事で行うプロセスを体感してくれたのではないでしょうか。
アイデアを「伝える」スケッチに挑戦
午後からは午前中に膨らませたイメージを、より具体的に「製図(スケッチ)」する時間に挑戦です 。
「施主さんの願いは叶えられているか?」「この広場の自然を活かせているか?」「みんなが安全に、楽しく過ごせるか?」
チームの仲間と話し合いながら、たくさんのアイデアを一枚の絵にまとめていきます。 最後はチームごとに構想を共有し 、お互いのアイデアの良いところを見つけ合いました。
子どもたちは建築の原点である「誰かの想いをカタチにする」 ことの楽しさや、自然から学ぶことの大切さを、より深く実感してくれたのではないかと感じています。
次回の活動も、どうぞお楽しみに!